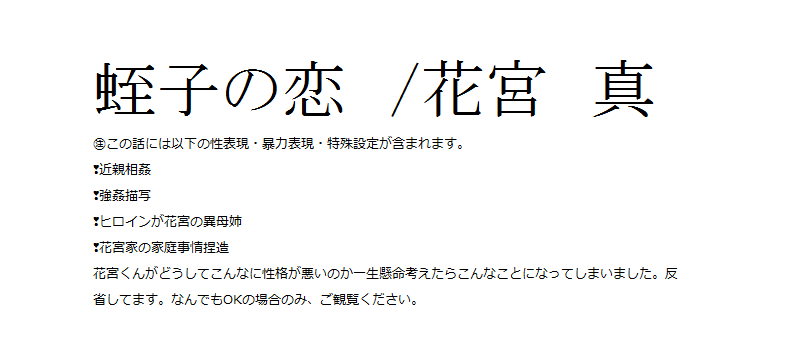 帰りたくない。けれど逃げるとして何処へ?という話だ。私が通っている高校は頭にお花が咲いたような能天気どもが運営するミッション系私立女子高で、校訓は「良妻賢母を育てる」、校則では染髪・ピアスは勿論「不純異性交遊」と「買い食い」と「寄り道」、「生徒同士の連絡先の交換」等諸々が禁止されており、どこかで誂たような均一な微笑みを湛えたまま勉学に励む女子生徒を朝8時から夕方5時ごろまで預かって家に帰す、教師による教師のための女子高生の箱庭なのである。育ちがよく善良な先生方におかれましては、校訓と校則が人をより善なる方向へ導くと信じていらっしゃるのでしょう。 長い黒髪をひっつめた独身妙齢の担任教師から「さんは模範生ですからね」と言われて風紀委員に推薦されたときは、目上の方に対して大変失礼ではあるものの笑いをこらえるのが大変であった。この鋭角的な眼鏡のきついオバサンは何かにつけて偉そうなことをいい、時々感極まったように聖書の一節をそらんじてみたりもするのだが、私が非処女で弟と性的関係を持っており、日常的に性交渉をし、暗い部屋で散々喘いで痙攣するほどイキまくり、気品と高潔の象徴である百合の花の校章が刺繍された制服に精子をぶっかけられて何枚もダメにしていることにも気づかず、徒に風紀を守らせたりなどしているのである。父の希望で入学した学校だが、下らないところです。おとうさん、あなたもわたしもいつも間違える。本当に何もかもを履き違え、間違え続ける私たち親子。死んだらきっと地獄に落ちるだろうが、罪を数えるにしてもどこから始めたらいいのかわからない程だ。 何から間違っていたと思う?と以前真に尋ねたことがある。14の夏、処女を喪失した夜の話だ。真の母と私たちの父の離婚が成立し、父と私が家を出ることが決まった日。普通そんな最低な日にそれ以上最低なことが起こると思うか?私たちは血がつながっていないという設定の、わりと仲良しの「姉弟」だった。私は「父の知り合いの忘れ形見で、養女として」この家に迎えられ、3歳から真と一緒に育ったのだ。少なくとも、父のシナリオでは、私はそういう存在だった。真。可愛い可愛い私の弟。小さいころはいつも、とことこと私の後ろをついて来た。蟻を執拗に踏みつぶしたり嫌いなクラスメイトを死ぬほどいじめたりしていたとあとになって聞かされたけれど、私の前ではいつもかわいい弟だった。家族が崩壊し母がわりの女性が他人になり、憎き父が石ころのように見えるようになっても、真はずっと私の弟だと思っていた。今となってはまるで夢みたいな話だが、真は私を姉さんと呼んでいたのだ。 誰もが息を潜めていたあの夜、真は私の部屋を礼儀正しく二度ノックして入室許可を得たうえで私の部屋に入ってきた。私は思春期だったのと、長年の疑念、つまり私が父と父の浮気相手の子供なのではないか、という疑念がいよいよ真実味を帯びたことで目に涙を浮かべていて、現実逃避がてら大好きな「ローマの休日」の映画を流していた。真は後ろ手にドアを閉めて「姉さん」と柔らかい声で言った。今思えばうさんくさいことこの上なかったが、私も子供だったので真の中学生らしからぬ腕に縋りついて「うん」と返事をした。ここからのことはもう超はっきり覚えているし一生忘れないし体調が悪くなると必ず夢に出てきて魘されるのだが、真はそのとき、氷のように冷えた指で私の腕をぐっと強くつかんで、すごく気持ちが悪い笑い方をした。そしてドアの傍の電気を消して私に足払いをかけて転ばせ、床に崩れ落ちた私の上に覆いかぶさると、くっくと笑いながら私の耳元にこう囁いたのである。 「なァ、オイ、アンタの所為だぜ。『姉さん』」 鈍器で頭をぶん殴られたような衝撃であった。ショックで動けずにいる私の腰をそっと抱いて、真は悪魔みたいに笑った。 「どんな気持ちだ?今、なあ」 どんな気持ちも何も、人生で一番最低な気持ちだった。息すらうまくできず、目からは勝手に涙が落ちてきた。何を考えていたのかは特に思い出せない。真は私の目尻に口づけて、それからシャツを引き裂くと首筋にきつく歯を立て、足の間に身体を滑り込ませて、真は笑いながら囁いた。「叫べよ、親父が飛んでくるぜ」。 結論から言って、私は叫ばなかった。真の唇はひどく冷たかった。手も冷たかった。爪が綺麗に切られていた。舌は熱かった。それ以外も。 これが私が処女膜を失った経緯である。最低な流れもここに極まれりだが、抵抗しなかったので和姦なのだろう、多分。ただめちゃくちゃ痛かった。イメージ的に、出産ぐらいの激痛であった。真は童貞だったのだろうか?もし童貞じゃなかったなら、それまでの相手の女の人に申し訳ないと思うレベルである。あと下着もボロボロになった。最低である。好き勝手に凌辱された体中がしびれるほど痛み軋んだ。 嵐のような暴虐が終わったあと、「何から間違ってたと思う?」と尋ねた私に、真はすごく汚い嘲笑を浮かべてこう返した。 「全部だろ、バァカ」 まあそうだ。私もそう思う。私たちはまったく最低の家族だった。そうだね、と私は笑った。 あの日以来私と真の関係は一切合切変わってしまった。真はもう私を姉とは呼ばないし、前みたいにノックをして部屋に入ってくることもないし、何も言うことをきいてくれたりしない。私と父の家の合鍵を勝手に作る。私のいない間に家に来る。 学校から帰ると、家の鍵が開いている。父はしばらくずっと戻っていない。玄関の靴で、真が来ているとわかる。寄り道をしたくても制服では禁止だ。だけど家に帰ったら不純な異性との性交が確定しているのに、一体私はどうするのがよいのだろう?だから学校関係者は浅薄だというのである。脱力感を覚えながら靴を脱ぐ。この家の空気はどこか湿気て陰気だ。風を通しても変わらないから、立地の問題なのかもしれない。自室のドアノブに手をかける。力を入れる前にドアが開く。バランスを崩した私の手を固い男の手が掬った。光をカーテンに遮られた暗い室内にに引き摺り込まれる。 部屋には音楽が流れていた。今日はテレビがついているのだ。子供のころから大好きなヒロインアニメのテーマソングだった。昔私より小さかった真と一緒に見ていた。今の私は私よりでかい真の腕に引き込まれてそのままベッドに倒されている。真は「こういうこと」を私が嫌がるとしっていて行うのである。私は初体験で大好きな「ローマの休日」をつけたままブチ犯されたことで、以来もうマジでオードリー・ヘプバーンの顔を見るのすら嫌になってしまったのだった。真に詰られて蔑まれて存在を全否定されながら犯されることにすっかり慣れた今でも彼女の出ている映像を見る気がしない。好きなものが減っていくのは悲しいことである。真のばらまく絶望はいつも懇切丁寧だ。このアニメもまた見れなくなってしまうんだろう。私の物をなんでも台無しにするのが大好きな真。真性のクズ。 ぼんやりと上を見ると、真は私を心底馬鹿にしたような目で見下げている。後ろの天井の染みは数えるのももう飽きた。真の手はいつも冷たい。爪が綺麗に切りそろえられている。昔から気難しい子だったけど、私には違ったはずだったのに。屈託なく笑ってくれたこともあったのに。黒い大きな目に私が映っている。私と真はあまり似ていない。手を伸ばして頬に触る。真は一度びくりとしたけれど、身を引いたりはしなかった。いやだなあ。アニメの歌が流れている。昔のことを思い出す。 「・・・真」 「・・・何だ」 あの日からもう、随分経って、真はすっかり大人の男の身体になってしまった。男にしては色白の頬を撫でて、首から肩へ降ろしていく。真はずっとバスケットボールをやっているらしい、筋肉質な身体だ。背も高い。顔も悪くない。じっと見つめているとたじろいだような目をする。私は笑ってしまいそうになる。私たちはどうして、こんなに最悪で、何もかも間違えているんだろう。どうして、普通になれないのだろう。 あのね、と私は言う。 「私、多分おとうさんの本当の娘だよ」 「ああ?知ってるに決まってんだろォが。そんなもん」 「私たち姉弟なんだよ」 「クハッ・・・散々犯されといて倫理観の心配かよ。ウチじゃ今更だろーが。オレはアンタを姉貴なんて思ったことはねえよ」 「でも私は姉さんなんだよ」 ピクリ、とこめかみに筋がたつ。顔色が青ざめて瞳が冷徹に燃える。真には2種類逆鱗が備わっていて、外側の1つは触ってもうまくいけば許してくれるが、もう一つ奥の方に、触られると恐慌を起こすものがある。明らかに今回は後者だった。私は最悪な女なので、真が一番言われたくないことがわかるし、一番言われたくないことを言うのである。幽鬼みたいに笑って。 「真、こんなことしても、何にもなんないんだよ」 左の頬に衝撃が走った。殴られたとわかったのは数秒後だ。首元を両手で押さえつけられて呼吸が苦しい。呻くと、少しだけ拘束が弱まった。ただ息の凍るような冷え切った声が吐き棄てられる。「うるせえな」制服のブレザーの釦が吹き飛んでいく。シャツを引きちられながらまくり上げられて下着が露出する。ラベンダーカラーの可愛いやつだから千切らないでほしいなあと思うが、真は私が嫌がることしかしないので言うことは聞いてくれないだろうと黙っていた。余計なことを言わなかったのが功を奏したのか、真はちゃんと背中に手を突っ込んでホックを外してくれる。そのときだけ、壊れ物に触るみたいに。笑ってしまう。 初めてのときはワイヤーブラジャーの形が変わってしまったのに。もしかしたらあの時、真も初めてだったのかもしれない。完全に初めてじゃなくても、ほとんど初めてに近いようなものだったはずだ。だってまだ中学1年生だったのだ、あのとき。唇が冷たかった。手が冷たかった。爪を切っていた。きつく抱きしめられると、真の心臓がうるさかった。今日だってそうだ。そしていつも、必ず電気を消してくれるところがかわいい。私はこの男の感情の形を知っている。笑ってしまうぐらい、真は正直で、だからこんなに惨めなのだ。私たちはどこから間違っていたのだろう。どこに戻れば、助かるんだろう。首筋に犬歯が食い込んでいく。そのまま噛みちぎって、今日で終わりにしてもいい。肩に腕を回すと、真は「畜生が」と耳元で呻いた。指が身体を這いまわる。舌が皮膚を撫でていく。息と体温があがって、触れた心臓が可哀想なほど鼓動している。「」そんなふうに呼ばないでほしい、私の家族はお前だけで良かったのに。ずっと姉と弟なら、きっとまともでいられたのになあ。涙が出てくる。感じてるからなのか、真がかわいそうだからなのか、ゴムつけてくれないからなのか、全部なのか、わからないでいる。 |